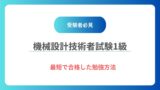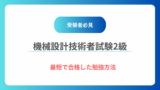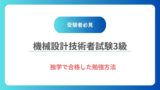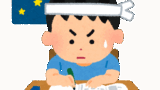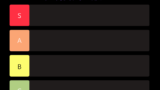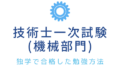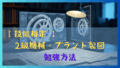R6年度 技能検定1級 機械・プラント製図に合格しましたので、攻略記事を書いていきたいと思います。これから練習を始める方、受検を検討している方の参考になれば幸いです。
なお、私は2DCADで受検しておりますので、手書きの方の参考にはならないかもしれません。予めご了承ください。
目次
概要
実技試験問題(計算問題を含む)及び課題図(機械装置を組み立てた状態の図面)から、指定された部品図をCADにより作成する。
試験時間:5時間
合格点
実技:60点
学科:65点
詳細は中央職業能力開発協会のHPよりご確認ください。
受検の目的
会社に言われて受けました。弊社では、昇級の際にこの技能検定や機械設計技術者試験の取得が必須となっています。その為、技術系の社員はほとんどの人がこの技能検定1級を取得しています。今後機械製図が減っていくかどうかは別として、受けなければなりませんでした。
前向きな理由としては、“技能”の証明が欲しかったからですかね。やはり一朝一夕で身につくものではないので、スキルのアピールになると考えました。
同様に、次の受検で合格したいという方に是非最後まで読んでいただきたいです。
勉強時間
実技:5ヶ月(16週)
学科:10時間
実技に関しては、時間というより「期間」となるかと思います。土曜日は丸々潰れてしまいますしね。。実技は9月中旬から練習を始めました。ほぼ毎週土曜日、年末年始も休まず練習しました。会社の練習スケジュールでは10月中旬からの開始でしたが、一度そのスケジュールで不合格になった為、同じではダメだと思い担当者に前倒しを要望しました。9月~11月までは、機械設計技術者試験の勉強も行っていましたので、かなりしんどかったです。自分で決めたことなんですけどね。下記は私の練習期間です。
| 9月3週 | 9月4週 | 10月1週 | 10月2週 | 10月3週 | 10月4週 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月1週 | 11月2週 | 11月3週 | 11月4週 | 12月1週 | 12月2週 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 12月3週 | 12月4週 | 1月1週 | 1月2週 | 1月3週 | 1月4週 |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
勉強方法
実技学科とも過去問をひたすら解きました。
前提ですが、
・本番で使用するCADで練習できる環境がある
・実技の過去問をA1で出力できること
・模範解答があること
以上が条件となります。私は過去問と模範解答とも、会社が用意してくれていたものを使用しました。
実技
1級は作図量が格段に多くなります。2級で優秀賞を取っていた人でも、1級は練習時に時間内で書ききれたことがほとんどなかったようです。私も同じでなかなか書ききれず、焦りを感じました。毎回の練習は5時間でやめてしまうのではなく、できるだけ最後まで書ききる方がよいです。1級は試験時間も長いので、集中力が落ちてきた終盤で本番でやるべきこと(仕上げ入力、風船入力、溶接入力など)に慣れておく必要があります。本番ではちゃんとやる、というのは練習として不十分です。「練習は本番のように、本番は練習のように」が受かるためのコツです。(部活並感)
2級と異なるのは溶接構造になることですね。風船や溶接記号を描く必要があります。よく「1級の方が溶接構造なので分かりやすい」と言われますが、個人的にそうは思わなかったです。確かに鋳物より溶接構造の方が実務で慣れていますが、溶接も1部材の形状の自由度が高いことから、どこまでが1-1でどこからが1-2かという境目がわかりづらいです。2級と比べて描く量が増えていますので、絶対的にCADの操作スピードは必要となります。1手の短縮を極めていきたいところです。積み重ねが大きな差になります。
また、私はMICRO CADAMでファンクションキーは使わず受検しましたので、その設定を記事にしています。こちらもよろしければご覧ください。
学科
実技が終わってからで間に合いますが、少し余裕がない気はします。意外と1週間みっちりやった方が気持ち的に安心です。他人の勉強時間に惑わされず、自分の進捗を見極めて足りない分は時間をかけて対応しましょう。私は10年分程度は解きました。その結果、余裕をもって合格することができました。
時間配分
以下は私の1級練習時の時間配分です。年度により若干異なりますので1つのサンプルとしてください。
| 作業 | 時間(分) |
| ①作図指示の把握 | 30 |
| ②計算 | 5 |
| ③マーキング | 5 |
| ④採寸 | 30 |
| ⑤部品①作図 | 100 |
| ⑥(部品②作図) | 30 |
| ⑦部品①寸法記入 | 60 |
| ⑧(部品②寸法記入) | 30 |
| 検図 | 10 |
| 合計 | 300 |
作図指示の把握
問題文で指示のあるボルトサイズ、重要寸法、幾何公差、仕上げ記号を課題図に書き込んでいきます。重要寸法部には大抵仕上げ記号も必要になりますので、同時に入れておいた方がよいでしょう。また、断面指示や矢視など、各面の作図指示を把握します。作図目がけて焦ってしまいがちですが、ここで指示の理解が疎かになってしまうと結果的に正しい作図ができませんので、あまり時間をかけすぎずにさっと指示を読んでいきます。
計算
ボルト本数の算出や公差計算など、さほど難しい計算はありませんが、わからなければ飛ばしてもOKです。時々、計算結果が課題図の寸法通りのパターンもありますので希望は持てます。計算結果が形状に関係する場合でも、その部分は計算の配点とみなされると聞いたことがあります。
マーキング
作図対象部品に色を塗って、形状を認識しやすくしていきます。1級は作図対象が多いため、作図対象を全て塗る必要はありません。最低限の色塗りでOKです。何重にもある線を全て塗る必要もありません。分かりづらい部分や作図を忘れてしまいそうな部分だけで十分かと思います。メインの部材は塗るのに時間がかかりますし、忘れることは少ないかと思います。また、色を塗りすぎると線(線種)が見づらくなるデメリットがあります。もちろん練習の序盤で、形状把握を優先するフェーズでは、時間を気にせず正確に把握する為丁寧に塗っていただいてOKです。慣れてくると色塗り不要になってくるので、練習の後半では色塗り無しでチャレンジしてみてもよいかと思います。
採寸(課題図に書き込む)
1級は1:2が多く、三角スケールの数値が5cm飛びなので読みづらいですが、測り直しがないようにさっと正確に採寸していきたいです。また、トレースで済むように1ヶ所に集中して記入しておきましょう。
部品①作図
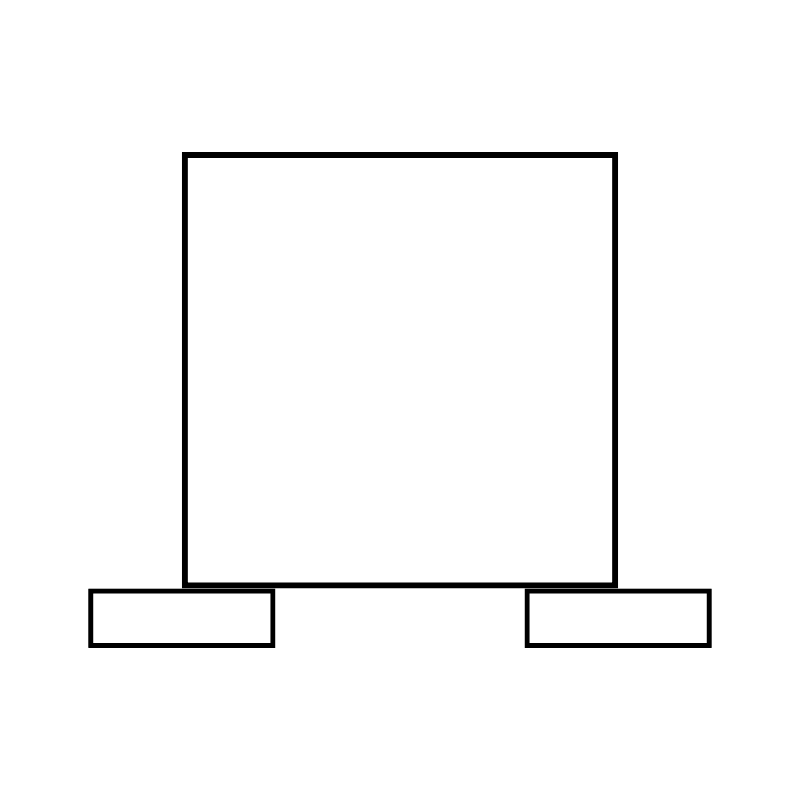
大抵は上図のような、箱に足が付いた形状が出題されます。複数年分過去問を解けば、ある程度傾向は掴めるようになるかと思います。形状がわかりづらい場合でも、わかる所から描いていけば見えてくることもあります。紙面上で悩むより、CADに落とし込んだ方が効率がよいです。本番でも同様に、極力手を動かして時間ロスを避けたいです。
部品②作図
軸やフタが多いですね。時々ややこしい物もありますが、多くは段々になっている部材かと思います。特に作図タイミングは気にしていませんでした。部品①が難しく手が止まってしまう場合は、先に②を書ききってから①に注力する流れでもよいかと思います。
寸法記入
重要寸法を優先的に記入していきましょう。重要寸法とは、・課題図に記載されている寸法・はめあい部の寸法です。重要寸法以外の一般寸法は割合、減点が小さいと聞いたことがあります。寸法の入れ方については、模範解答と一致していなくても、足し合わせて同じになる入れ方であれば問題ないと聞きました。
仕上げ記号、幾何公差、風船、溶接記号
溶接記号と仕上げ記号は、それぞれ1つも記入されていない場合、特別減点されます。正誤問わず、1つでも記入されていれば特別減点にはならないようです。
仕上げ記号については寸法記入と同時でOKです。はめあい部の1.6等、後回しにすると抜けてしまうリスクがあります。1つあたりの減点は少ないかもしれませんが、減点方式の採点である以上は可能な限り減点は避けたいです。幾何公差については、問題文で指示がありますので必ず記入するようにしましょう。データム基準や、公差の数値、数値の前にφをつけるか否か、記号自体の誤りなど注意しましょう。
検図
検図の時間はほとんど取れないかと思いますが、やはりわずかでも見直せると細かいミスに気づき、減点を防ぐことができます。
持ち込み可能な道具
持ち込み可能な道具が受験案内などに記載があります。以下で紹介する物以外に、コンパスも持ち込み可能でしたが、私は使いませんでした。
三角スケール
三角スケールは1級に多い1:2に対応する為必須ですね。長さは30cmが望ましいですね。寸法の採り方によっては、30cmでも足りない年度もありました。
テンプレート
Rを測るのに使います。問題が1:2の場合、読み取った数値を2倍とする必要があります。R3,4,5など、よく出るサイズはあるので、±2mmの誤差まで許容されることを考えると、あまり神経質に測る必要はないと思います。同じ部品なら、大体Rサイズも統一されていますしね。
分度器
斜めの形状や、穴中心の角度を測る時に使いました。
消せるペン
部品①、②の抜き出しと、重要寸法の記入に使います。①、②がはめあう部分もありますので、どちらの寸法かを見分ける為にもう1色あってもよいかと思います。私はフリクションボールペンを3色使っていました。蛍光ペンや色鉛筆など、使いやすい物で良いかと思います。色は赤と青とオレンジを使っていました。自分が認識できれば何色でもよいと思いますが、①、②で似た色だとやはり見づらいです。重要寸法も目立つ色にして、記入漏れを防ぎましょう。
シャーペン
重要寸法以外の一般寸法の記入や、計算問題に使いました。私は上記の物を使っていました。書きやすいのでおすすめです。
マウス
持参物一覧には書いてありませんが、私が受検する会場では持ち込み可能でした。私は会場に用意されている物を使用しましたが、普段の練習で使い慣れたマウスを持ち込むことを”強く”おすすめします。私も普段は「弘法筆を選ばず」の考えですが、ここでは適用外。理由は、会場を悪く言うつもりはありませんが、用意されていたマウスがかなり使いづらく、触った瞬間に相当焦りました。左右ボタンがクリックの度に大きくパカパカとなり、それに付随してクリックのレスポンスも悪く非常に苦戦しました。その為、準備時間の30分で必死に手を動かして慣れました。このような機器ガチャを避けるには、マウスを持ち込むことをおすすめします。自身の努力の成果をマウスに邪魔されては元も子もありません。なお、Bluetooth接続でドライバのインストールがいるような物はNGのようでした。
電卓(プログラム機能がないもの)
関数電卓は持ち込みOKです。筆者はプログラム機能は特に使っていませんので、機能を有しているかは気にせずに持ち込みました。
苦戦している方へ
複数回受検されている方、弊社でも多いです。練習回数が10回未満など少ない方は言うまでもありませんが、私とほぼ同じ回数練習されていた方でも、不合格になっている人もいます。練習での完成度は私よりも高かったです。CAD操作も速く、形状理解も問題無さそうでした。私が思うに、新規問題への対応力が不足しているようです。
課題図を見る→模範解答を思い浮かべる
ではなく、
課題図を見る→3Dをイメージする
訓練が必要かと思います。断面指示も含めてです。練習を繰り返すうちに模範解答を覚えることは問題ありませんし、模範解答のトレースも操作スピードを上げるのに有効な練習です。しかし、意識的に3Dを介することで本番での対応力を養う必要があります。また、
・CAD操作は、始めは時間がかかっても短縮できる操作を身につける
・形状把握が苦手であれば、課題図と解答図を見比べてパターンを理解する
・難しい作図指示の年度を重点的に練習する(課題図と逆視点を作図するパターンなど)
以上のことに取り組んでみることをおすすめします。これらをやろうとすると、1級の場合は毎回の練習時間だけではカバーしきれないと思いますので、平日の空き時間や休日の練習外の時間も活用しましょう。練習期間も長くとりましょう。会社から提示された練習期間に沿って練習しているだけでは乗り越えられない壁もあります。私はそうだったので、人よりもやらなければならないことを理解して練習に取り組みました。それでも合格することはできました。この試験で必要な形状認識は、誰でも初めからできるわけではないのです。このことは、東大卒の素材さんの有料note(努力型高学歴が考える最強の幼児教育)で知ることができました。私自身も、理数系が得意な人は苦労しないんだと思っていました。もちろん得手不得手はあるので、得意な人もいるとは思います。(余談ですが、弊社の別事業所にいる高専首席は、2週間の練習で合格していました。)この試験に必要なのはそういった能力ですので、不出来を気に病む必要はなく、その時間があればむしろ1年分でも多く過去問を解いた方が有意義です。
モチベーションが上がらない時は、くろたかさんのVoicyを聞いてみるのもおすすめです。合格した今聞いても、励ましてもらえます。技能検定に限らず、何かの試験を頑張っている人にぜひ聞いてほしい放送です。
最後に
実技は非常に難易度が高いです。私も2度受検しましたが、2度目も自信を持って合格できるというところまでなかなか辿り着きませんでした。運よく合格できたと思います。結果を知った時は、機械設計技術者試験1級に受かった時より嬉しかったです。なによりこの試験、普段は無いA1図面と対峙する為、ロマンを感じました。皆さんもぜひ、合格を目指して頑張ってくださいね。最後まで読んでいただきありがとうございました。
技能検定1級 機械プラント製図に合格しました✨
— とけい@設計 (@tokei_chu) May 23, 2025
機械設計技術者試験1級と同年合格です💯
使用CADはMICROCADAMで、ファンクションキーは使っていません。
会社の人にも無理だと言われたけど、自分を信じて頑張ってよかった!
二兎を追う者は二兎とも得る🔥 https://t.co/8kwmenzGpp pic.twitter.com/XbG4Tn2PJD