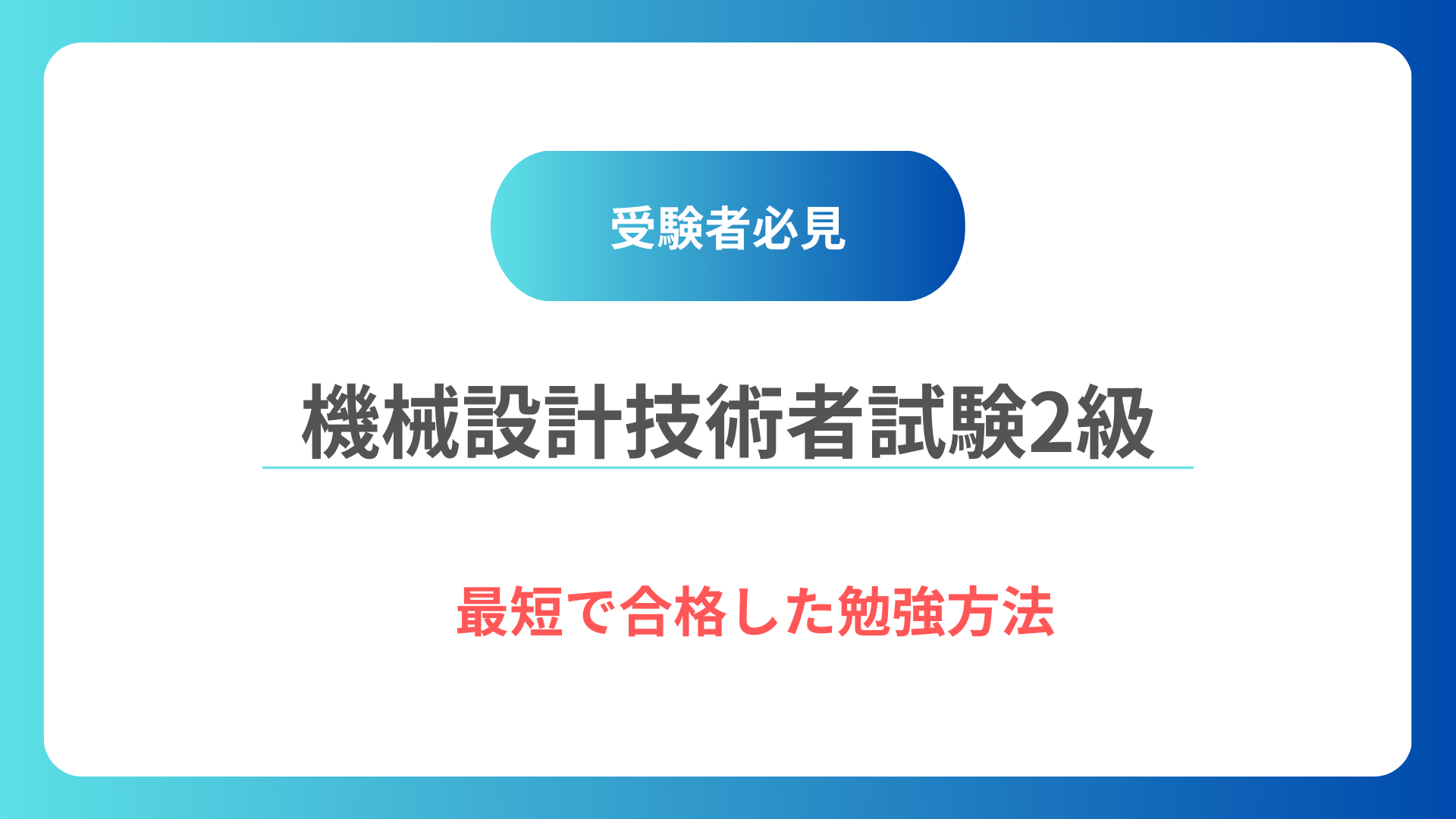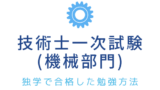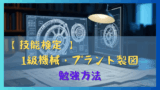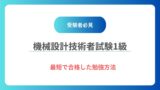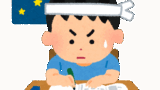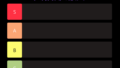かろうじて高卒レベルの学力の私が、機械設計技術者試験2級に独学で一発合格した勉強方法とおすすめ参考書を紹介します。受験資格を得てすぐに受験しました。3級同様、過去問ベースの勉強で取得可能です。
ステップアップしていく方がスムーズですので、3級を取得していない方は3級から受験されることをおすすめします。成功体験を得ることで勉強の継続に役立ってきます。
Follow @tokei_chu目次
試験概要
基本設計に基づき、機械及び装置の機能・構造・機構等の具体化を図る計画設計業務を行なえる能力に達した技術者を対象とした試験を行ないます。
<受験資格>
| 受験資格 | 最終学歴 | 直接受験 | 3級合格者 | |
|---|---|---|---|---|
| 工学系 | 大学(院)・高専専攻科・高度専門士・職業能力開発総合大学校(旧職業訓練大学校)・職業能力開発大学校 | 3年 | 2年 | |
| 短大・高専・専門学校・職業能力開発短期大学(旧職業訓練短期大学校)・「職業能力開発校(旧職業訓練校)(高校卒業後、2年制)」 | 5年 | 3年 | ||
| その他(上記以外) | 7年 | 4年 | ||
<実施日>
令和7年11月16日(日)
令和7年度 2級試験科目時間割(試験時間 9:30~16:30)
※年度によって科目の組み合わせや解答方法が変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
| 第1時限 9:30~11:40 | 機械設計分野熱・流体分野メカトロニクス分野 原則マークシート方式、一部記述式となる場合あり。 |
|---|---|
| 第2時限 12:40~14:40 | 力学分野材料・加工分野環境・安全分野 原則マークシート方式、一部記述式となる場合あり。 |
| 第3時限 15:00~16:30 | 応用・総合は記述式解答方式 |
| 科目 | 機械工学基礎 機構学・機械要素設計、機械力学、制御工学、工業材料、材料力学、流体・熱工学、工作科目 ①機械設計分野 :機構学、機械要素設計、機械製図、関連問題 ②力学分野 :機械力学、材料力学、関連問題 ③熱・流体分野 :熱工学、流体工学、関連問題 ④材料・加工分野 :工業材料、工作法、関連問題 ⑤メカトロニクス分野 :制御工学、デジタル制御、RPA、自動化技術、他 ⑥環境・安全分野 :機械設計技術者としての環境・安全の知識 ⑦応用・総合 :機械工学基礎、機械工業基礎に関する知識の設計への応用ならびに総合能力。記述式問題 |
|---|
<受験料>
22,000円(税込み)
<合格率>
年度によって異なりますが、3~4割程度です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2024年 | 560人 | 247人 | 44.1% |
| 2023年 | 574人 | 234人 | 40.8% |
| 2022年 | 629人 | 268人 | 42.6% |
| 2021年 | 621人 | 256人 | 41.2% |
| 2020年 | 561人 | 183人 | 32.6% |
詳しくは日本機械設計工業会のHPを確認してください。
勉強時間
2級は約400時間勉強しました。
勉強開始は2月頃にパラパラと過去問を眺める程度開始しました。
平日は9時から21時まで仕事の毎日でしたので、1日合計1時間勉強できれば御の字でした。
その為、休日に集中して取り組みました。9月以降、土日は4~8時間勉強しました。
また、2級は技術士一次試験と並行で勉強しました。両方同年に合格することができました。
さらに、10月の中旬から技能検定一級機械プラント製図の実技練習も並行していましたが、こちらは同年度は不合格でした。
技術士一次試験、技能検定の記事も掲載しています。
勉強方法
過去問10年分を3周解きました。ただし、応用総合は解き方を覚えるまで何度も繰り返し解きました。過去問は3年分程度自費で購入しており、残りは会社にあったものを借りました。
過去問を解く流れとしては、応用総合を先に始めるのがおすすめです。とにかく周回して、解き方を覚えるしかありません。計算で疲れたら暗記の対策をしましょう。「先に暗記を始めても試験直前に忘れたら意味ない」という方もおられますが、何度も目に触れることが大事ですので、決して無駄にはなりません。1周めで挫折してしまうか、割り切って2周め、3周めを取り組めるかが勝負の分かれ目です。
応用総合は順を追って計算していかなければならず、過去問の解説も長く面くらいましたが、1つひとつ公式や解法パターンを暗記していきました。
この試験全体に言えることかもしれませんが、過去問の解説を見ても理解ができないものは「そういうものだと割り切って覚える」か「一旦諦める」でOKです。
問題数も多く、範囲も広い為全てを完璧に覚えようとするのは効率が悪いです。
なかには過去に一度しか出ていないような形式の厄介な問題があり、そういった問題に長い時間をかけるのはもったいないです。初見では皆解けないだろうと割り切って、過去問でも頻出の問題を確実に解けるようにする方が効率的です。無論、厄介な問題の類題が出題される可能性もありますので、余力があれば解けるようにしておくのがベストです。
過去問の入手方法
日本機械設計工業会のHPから入手する
HPより最新の過去問題と一部解答を閲覧することができます。不足する分は電子書籍か紙の過去問集を購入しましょう。
過去問集(紙書籍)を購入する
過去問題が解答付きで販売されています。ネットで購入可能です。
上記の本は全級併せて掲載されており、不要な人にとっては使いにくいと思いますが、後にステップアップする際には必要になってきます。
科目ごとのポイントとおすすめ参考書
私は基本的に過去問を周回しただけですので、参考書で勉強はほとんどしませんでした。しかし、3級受験時から所持していた物で2級にも役立つ書籍などを紹介したいと思います。入手可能な限りの過去問と、これらを活用していただければと思います。
機械設計分野
従来科目である「機構学・要素設計」の名称変更といったところでしょうか。ねじ、リンク、ベルト、カムなどが出題されています。私が受験したR5年はカムについて出題されました。過去問を数年見ると、そろそろカムが出そうかなと予想できました。直近で出題されていない項目に山を張るのはアリかと思います。対策としては「機構学・要素設計」までと変わらずで十分です。余弦定理を使う問題であったり、数学の公式を引っかける内容が出題されています。高校までの数学で、過去問の解説で使われているものをカバーできていれば最低限OKかと思います。数学知識まで深追いするときりがないです。
この本はタイトルの通り設計の教科書と言える内容ですので、持っておいて損は無いです。機械要素とその主要公式が載っています。
機構学に特化した本です。カム、リンク、歯車のほか、摩擦伝動、巻掛け伝動などについて載っています。持っていると、実務でも役立つかと思います。
熱・流体分野
名前の通り、熱力学と流体力学がまとまった感じですね。そもそもこの2分野、3級の時からまともに参考書で勉強していませんでした。過去問類題や語句問題が出なければ諦めるつもりでした。その分他が簡単なはずですので。
私が受験した年には、過去問に出ていなかった新規問題で、技術士一次試験の専門科目の勉強をしていたので対応できた問題がありました。余力があれば、取り組むことをおすすめします。
流体力学の概念をつかむのによいと思います。難しい式もあまり使われておらず、なんとか読む気になります。
熱力学は真面目に解こうとするとしんどかったです。過去問でよく見る、熱力学第一/第二法則、カルノーサイクル、ランキンサイクル等が載っていましたので、最低限の流し読みをしました。
メカトロニクス分野
語句問題が多めです。センサの種類やシリンダの構造、ステッピングモータ、シーケンス制御やPLCに等について出題されています。従来までの制御工学の対策で事足りるかと思います。わからない語句はネットで検索して、周辺知識も併せて覚えておきましょう。
この本はよくオススメされていますね。私は買っていません。制御工学は語句だけ覚えて、計算問題は捨てていました。お値段も結構するので、試験合格が目的ならコスパ悪いなと。。
力学分野
機械力学と材料力学ですね。対策も個々の従来までと変わらずで問題ないかと思います。新規の問題への対策は、技術士一次試験の専門科目の過去問が有効かと思います。時間に余裕があれば、取り組んでみてください。
2級の過去問を繰り返し解いていると、↑の本の内容はほぼ理解できるようになってきます。そうなると合格レベルの実力が付いているかと思います。
この本は、2級の勉強を始めたばかりの頃に読みました。3級受験時は正直、力学分野は自信が無いままラッキーパンチで受かってしまいましたので、2級では理解を深めるために基礎からやり直しました。力のかかり方のイメージを掴めるようになりますので、読んでよかったと思います。この試験では高校物理レベルの問題も多々ありますので、復習の意味でもおすすめです。
材料・加工分野
工業材料と工作法ですね。過去問を軸に、わからない語句はネットで調べればOKです。
この本は試験対策としてはあまり使いませんでした。しかし、あやふやな知識が整理できますので持っていて損は無いです。
環境・安全分野
過去問と、経済産業省のものづくり白書(概要)を読んでおくとよいです。ものづくり白書は1級の小論文にも役立ちます。また、ISO 12100について毎年出題されていますね。この科目は満点を狙いたいところです。
応用・総合
筆記となりますが、何かしら考え方、解き方があっていれば部分点をもらえるかと思います。事実、私は各問題で完答できていなかったですが、なんとか合格することができました。例えば(1)の答えを(2)で使うように順を追って計算していく問題で、(1)の答えが間違っていても、(2)の解き方があっていれば部分点はもらえると思います。公にはなっていない為定かではありませんが、合格者の話を聞いても概ねそのような感じです。そして、応用総合をしっかり勉強していると、1級受験時かなり楽になります。(1級を受験するのであれば、2級に受かった直後がおすすめです。)
全体
試験直前に見つけた為、購入はしなかったのですが、過去問で出てくる公式が多く載っていたかと思います。ある程度公式がまとまっている書籍が欲しいという方にはおすすめできるかと思います。自分で公式集を作る手間が省けますしね。
こちらも対策本としては有名ですよね。オーム社に変わってから内容がアップデートされているでしょうか?(旧版と読み比べていないので、間違っていたらすみません。)私はどちらも持っていないのですが、本屋でオーム社版を見てみると、説明が詳細になっていた印象を受けました。購入される際は過去問を解いてみて、ほしい部分の解説が自分にあっているかを見極めて購入するのをおすすめします。
合格ライン
合格ラインは公表されていませんが、6割程度の正答が必要かと思われます。私が合格した際は、1,2限でそれぞれ7割、応用総合で完答の手ごたえがあったのは5割程度で、部分点がどの程度もらえていたかは定かではありませんが、トータルで6割を超えていたのかと思います。
最後に
私は1級まで取得していますが、2級が1番苦労しました。勉強時間も最も長かったです。人によると思いますので、あくまでご自身の進捗に合わせて勉強を進めていきましょう。対策は長期に及ぶと思いますので、後悔しないように。
また、蛇足ですが2級に合格してから転職サイトで大手メーカーより開発設計職にてスカウトが来るようになりました(未応募)。学歴もなく、今大した企業に所属しているわけでもありません。恐らく資格と実務経験次第で、選択肢は広がってくるものと思います。今の努力は決して無駄になりませんので、自分なりの精一杯を積み重ねて行きましょう。
機械設計技術者試験を頑張る皆様
— とけい@設計 (@tokei_chu) April 17, 2025
転職で有利になりますよ
私は大した学歴も無く、今大した企業でも無いですが2級を取ったあたりで大手メーカーから開発設計職でスカウトが来るようになりました
例)完成車メーカー3社、メガサプライヤー1社他
計算力の証明になるので学歴コンプは破壊できますよ😁↓