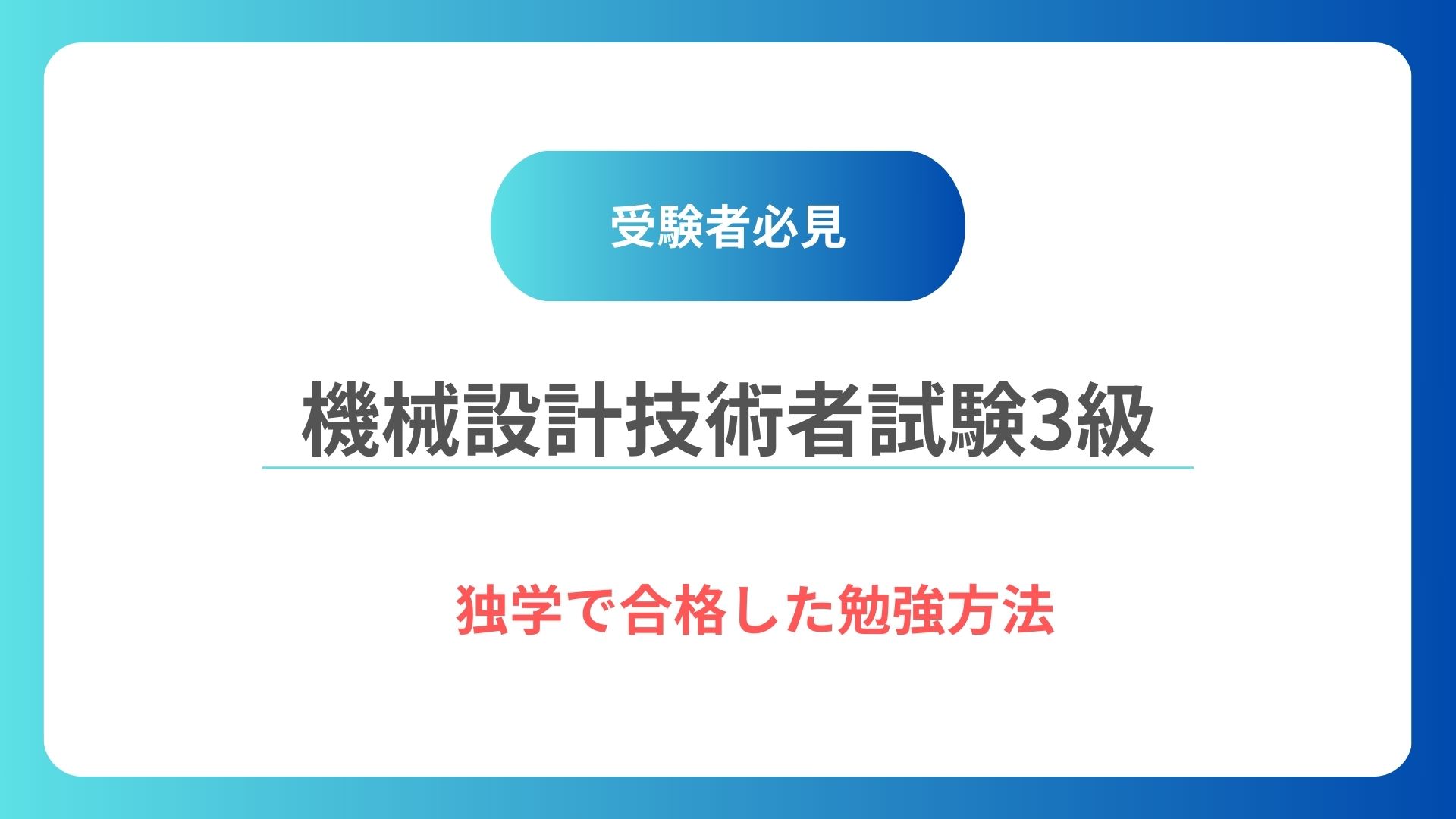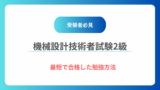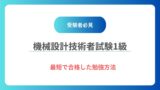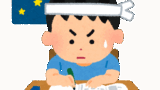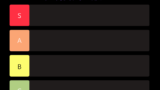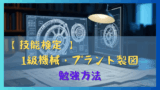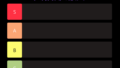かろうじて高卒レベルの学力だった私が独学で機械設計技術者試験3級に合格した勉強方法と、使用した参考書を公開します。受験される方のお役に立てれば幸いです。
Follow @tokei_chu目次
試験概要
機械や装置の詳細設計の補佐、ならびに関連する製図等の業務を行なえる能力に達した技術者、または機械設計全般の基礎知識を習得した学生を対象とした試験を行ないます。
<受験資格>
実務経験不要。学生の方でも受験できます。
<実施日>
令和7年11月16日(日)
令和7年度 3級試験科目時間割(試験時間 12:00~16:20)
※年度によって科目の組み合わせや解答方法が変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
| 第1時限 12:00~14:00 | 機構学・機械要素設計、流体工学、工作法、機械製図 全科目、マークシート方式 |
|---|---|
| 第2時限 14:20~16:20 | 材料力学、機械力学、熱工学、制御工学、工業材料 全科目、マークシート方式 |
| 科目 | 機械工学基礎 機構学・機械要素設計、機械力学、制御工学、工業材料、材料力学、流体・熱工学、工作法、機械製図 |
|---|
<受験料>
8800円(税込み)
<合格率>
年度によって異なりますが、3~5割程度です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2024年 | 1,763人 | 900人 | 51.0% |
| 2023年 | 1,838人 | 865人 | 47.1% |
| 2022年 | 2,049人 | 780人 | 38.1% |
| 2021年 | 2,110人 | 910人 | 43.1% |
| 2020年 | 1,927人 | 719人 | 37.3% |
詳しくは日本機械設計工業会のHPを確認してください。
おすすめのYoutubeチャンネル
機械設計技術者試験1級、技術士(機械部門)を取得しておられるくろたかさんがわかりやすく解説してくださっています。私も受験時には大変お世話になりました。チャンネル登録よろしくお願いします。
勉強時間
約300時間程度かかりました。勉強開始は3月頃だったかと思います。学力に自信が無い方は早めに始めましょう。私は9時から21時まで仕事の毎日でしたので、平日は合計1時間できれば御の字、8月以降の土日は最低4時間~可能な限りを勉強にあてていました。
勉強方法
過去問10年分をひたすら解きました。
まず最新の過去問を解いてみて、どのような問題が出題されているのか把握します。この時、正答率や時間は全く気にする必要ありません。私も最初は全く解けませんでした。しかし、複数年分を繰り返すうちに解き方を覚えられるようになりました。初学者の場合、10年分を最低3周は必要かと思います。自費で購入するとなるとかなり費用がかかってしまいますが、資格を取得する為に必要な出費は割り切った方が効率的です。
過去問がそのまま出ることはほぼありませんが、古い過去問(5年、10年前)の類題が出題されることは全級で多々あります。逆にいうと、1年前の過去問などはまず類題が出ないので、流す程度でよいかもしれません。
(余談ですが、3級↔2級、2級↔1級などのように直近の前後の級の類題が出題される場合もあります。余裕がある場合、取り組んでおくとステップアップもスムーズになります。)
過去問の入手方法
日本機械設計工業会のHPから入手する
HPより最新の過去問題と一部解答を閲覧することができます。不足する分は電子書籍か紙の過去問集を購入しましょう。
過去問集(紙書籍)を購入する
過去問題が解答付きで販売されています。ネットで購入可能です。
上記の本は1級2級併せて掲載されており、不要な人にとっては使いにくいと思いますが、後にステップアップする際には必要になってきます。
こちらの本は3級のみが3年分まとまっています。この4冊で12年分が解けるので、繰り返し解けばかなりの対策になるかと思います。
科目ごとのポイントとおすすめ参考書
注意すべき点としては、参考書を頭から解いてはいけません。過去問の解説で理解しづらかった箇所の補強として使ってください。技術に関する情報はなかなかネットで正しい情報が得られにくいですので、書籍で確認することをおすすめします。
機構学・要素設計
歯車やねじなど、機械要素全般について主要公式と共に掲載されています。そのうえ表も多く載っており、2級や1級は表から読み取って計算を進めていく問題が出題されますので、見慣れておくと助けになります。この本はまさしく設計者にとって教科書と言える本です。合格後も役立ちますので、読んでみることをおすすめします。
機構学に特化した本です。カム、リンク、歯車のほか、摩擦伝動、巻掛け伝動などについて載っています。持っていると、実務でも役立つかと思います。
機械力学
過去問の類題が多く載っています。例題も多めですがやはり教科書感が強く、私には少し上滑りしていました。あまりこの本の解説で理解が深まった実感は得られませんでした。
この本は買ってよかったです。なぜなら私は高校で生物選択でしたので、物理は基礎から学びなおす必要がありました。この試験は高校物理レベルの問題も多々出題されていますので、復習の意味でも役に立ちます。物理の参考書を調べているうちに、阪大卒Youtuberのはなおさんもおすすめしていることを知りました。「この本で物理がわからなかったら、物理を諦めるしかない」とおっしゃっているほどです。私もこの本のおかげでなんとか物理を諦めずに済みました。苦手意識のある方はぜひ一度読んでみてください!
この本も有名ですね。しかし私には合わなかったです。試験に受かるのが目的であればこの本の例題を真面目に解くより、過去問で頻出の解法を覚える方が効率的だと感じたからです。もちろん解いておくことで新規問題への対応力は身につくかと思いますし、物理を専攻してきた人たちにはこの本の内容のような積み重ねがあるのかと思います。私はあくまで試験の合格が目的でしたので、購入したもののほとんど使いませんでした。
制御工学
上記の本は購入していないのですが、有名な本ですので制御工学で何か書籍が欲しいという方はチェックしてみてはいかがでしょうか。私は計算は捨てていました、、、試験に受かるだけであれば計算は解けなくても大丈夫です。出題数も少ないので。(制御の計算を真面目に解ける人を尊敬します。)ですが、語句問題は過去問の範囲を全て覚えるようにしていました。わからない語句はネットで調べて覚えました。
工業材料
この科目は得点源ですね。新規の問題が出題されると覚えていなければ太刀打ちできませんが、およそ4-6割は過去問から出題されますので+αで周辺知識を覚えておくことで、安定して合格ラインに到達できるようになるかと思います。見慣れた語句であれば100%解答したいところです。わからない語句はネットで調べれば大抵答えが出てきます。
上記の本は「工業材料の書籍を一冊持っておきたい」という方に強くおすすめします。試験勉強時は流す程度に知識の補強で使っていましたが、合格後も読むのが楽しいです。
材料力学
計算科目の中では得点源でしょうか。基礎的な公式を覚えれば小問のうち1,2問は取れるかと思います。もし本番で難しくても諦めてしまわず、消去法で絞っていきましょう。
流体工学
過去問の類題が多く載っていました。解説も易しめです。流体工学のテキストとしてはこれしか持っていません。学生の頃に学んだこともなかったので、この本の内容で十分に感じました。この本も最初から最後まで解くのではなく、過去問のわからない部分の補強として使うのがベストです。流体工学はネットで調べてもドンピシャの答えが得られることが少なかったです。そういった時にこの本が役立ちました。
熱力学
この本はあまり読まなかったですね。一応購入していましたのでおすすめとして。熱力学も難しい問題は捨てていましたし、語句の穴埋め問題は文章の繋がりである程度解けましたので、そういった問題や、式が与えられており代入すれば解けるようなものに賭けていました。全体的にいずれかの科目の計算が難しければ、いずれかは語句問題になる印象がありますので、上記の対策としていました。
工作法
この本はタイトルの通りわかりやくてよかったですね。過去問の内容も多く掲載されていました。しかし、全てが網羅されているわけではありませんので載っていない部分はネットで調べる必要があります。基礎的な内容である為、2級では使うことはありませんでした。
こちらも有名な「実際の設計」シリーズですね。私はまだ購入していませんが、後ほど読んでみたいと思っています。書籍の紹介まで。
機械製図
製図は得点源ですね。満点を狙いましょう。特に計算に自信がない方はここで引っ張っておくのが賢明です。私は試験が始まったら、製図から取り掛かった覚えがあります。製図の出来栄えで安心したかったからですかね。
仕事で図面を描いている人であれば勉強しやすいと思いますが、仕事では旧JISを使っていたり独自の描き方をしている場合があるので、試験向けに知識をインプットする必要があるかと思います。ノー勉は危険。
こちらも有名なシリーズですね。非常に易しく書かれていますので、是非確認してみてください。
全体
2級受験時に見つけたのですが、3級にも役立つと思います。過去問で出てくる公式が多く載っています。ある程度公式がまとまっている書籍が欲しいという方にはおすすめです。
こちらも対策本としては有名ですよね。ただ、これ1冊で対策OKという物ではありません。試験では、この本に載っていないこともバンバン聞いてきます。もし読むのであれば、勉強開始時に読むのをおすすめします。
合格ライン
概ね6割が合格ラインと考えていただいて差し支えないです。公表はされていません。私が合格した時は、全科目のトータルで70%を超えていました。(奇跡)
会社の先輩にも「半分くらいで受かった」と言う人も数名います。(各級)
取れる問題を確実に取れるようにする
範囲がとても広いので、基礎から固めようと参考書を頭から解き始めてはいけません。
過去問の解説を読んで、少し頑張れば覚えられそうだなという問題を重点的に覚えます。
優先順位としては
機械製図→(工業材料/工作法)→機構学→(材力/機力)→(流体/熱力)→制御工学
といったところでしょうか。製図は満点を狙いましょう。実務にも役立ちます。
やはり計算科目を先に始めるのが効率的でしょうか。
ただ、計算が難しく進捗が悪い場合の息抜きとして暗記科目を進めるのもありだと思います。何事も大切なのは「毎日継続すること」です。
時間が経つと忘れてしまうのは確かですが、繰り返し目に触れるスパンを短く、回数を増やしていけば最初に取り組んだ分は決して無駄になりません。
試験当日
関数電卓の持ち込みは可能です。
試験開始後、40分経過すると途中退室可能になります。(ただし途中退室した場合はその時限で再び席に戻ることはできません。手洗いに行き、戻ることは可能です。)水分補給も可能なようでした。
最後に
この記事を読んだ後、すぐに過去問を解き始めることができれば合格へ近づくこと間違いなしです!
道のりは長いと思いますが、努力されたことが必ずあなたの支えになります。例え結果が出なくとも、努力は無駄になりません。あなたの努力が報われることを心から願っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
機械設計技術者試験を頑張る皆様
— とけい@設計 (@tokei_chu) April 17, 2025
転職で有利になりますよ
私は大した学歴も無く、今大した企業でも無いですが2級を取ったあたりで大手メーカーから開発設計職でスカウトが来るようになりました
例)完成車メーカー3社、メガサプライヤー1社他
計算力の証明になるので学歴コンプは破壊できますよ😁↓