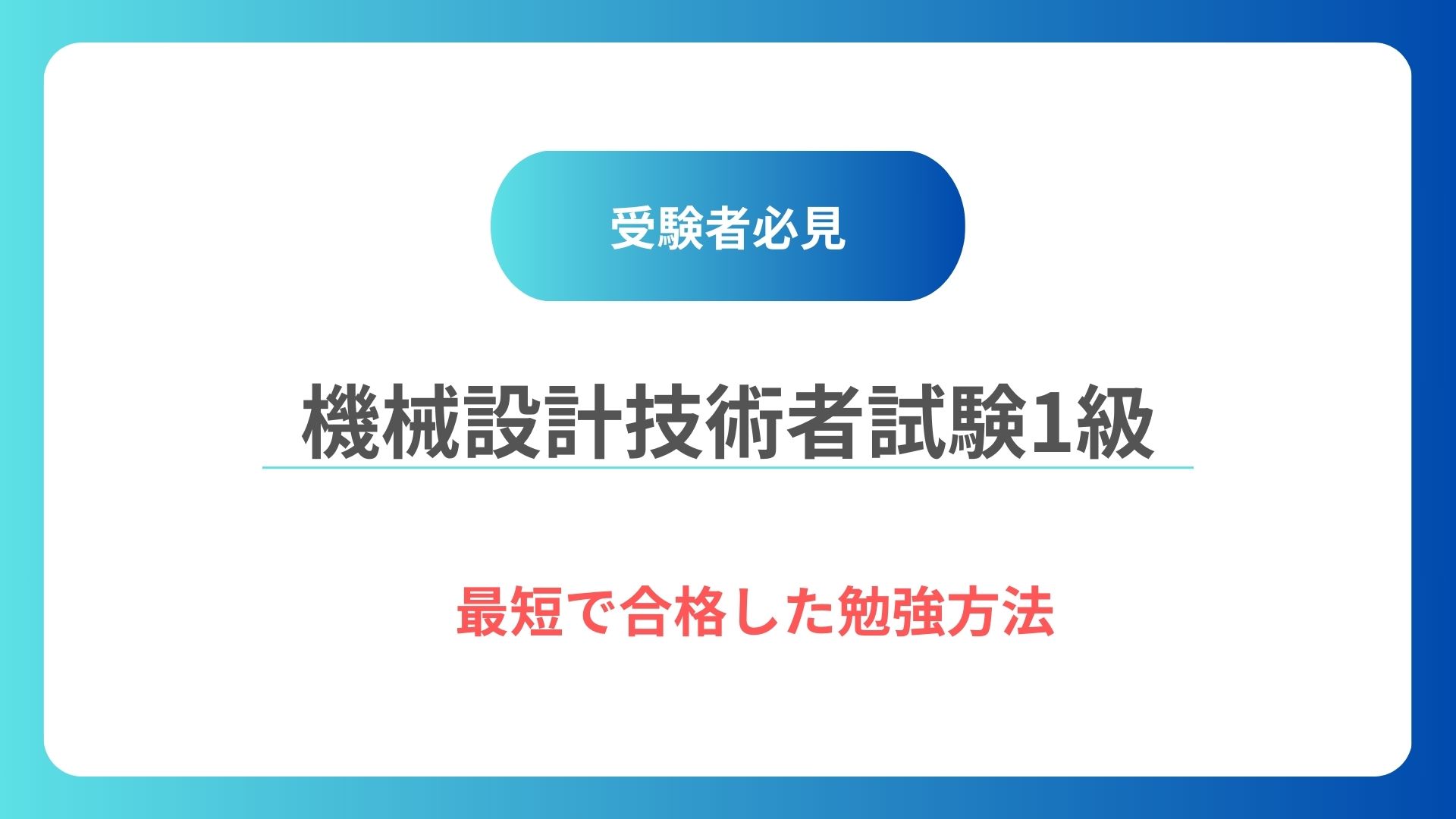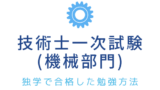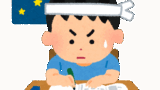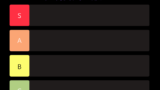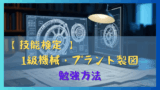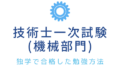かろうじて高卒程度の学力だった私が、令和6年度機械設計技術者試験1級に合格したのでその勉強方法を公開します。受験資格を得て最短1発で合格しましたので、次の受験で絶対に受かりたいという方は是非参考にしていただければと思います。3級や2級同様、1級も過去問を繰り返し解くことで合格可能です。
私は2級に合格した翌年に1級に合格しました。1級の計算問題は2級と大差ない部分もある為、可能であれば間隔を開けずに受けることをおすすめします。
Follow @tokei_chu目次
試験概要
機械及び装置の基本仕様決定に必要な計算、構想図の作成等の基本設計業務を行なえる能力に達した技術者を対象とした試験を行ないます。
<受験資格>
| 受験資格 | 最終学歴 | 直接受験 (※要審査) | 2級取得者 | |
|---|---|---|---|---|
| 工学系 | 大学(院)・高専専攻科・高度専門士・職業能力開発総合大学校(旧職業訓練大学校)・職業能力開発大学校 | 5年 | 2級取得後、 次年度から受験可能 | |
| 短大・高専・専門学校・職業能力開発短期大学(旧職業訓練短期大学校)・「職業能力開発校(旧職業訓練校)(高校卒業後、2年制)」 | 7年 | |||
| その他(上記以外) | 10年 | |||
| 受験料 | ||||
<実施日>
令和7年11月16日(日)
令和7年度 1級試験科目時間割(試験時間 9:30~16:30)
※年度によって科目の組み合わせや解答方法が変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
| 第1時限 9:30~11:40 | 設計管理関連課題、機械設計基礎課題、環境経営関連課題 全て記述式解答 |
|---|---|
| 第2時限 12:40~14:40 | 実技課題(問題選択方式) 全て記述式解答 出題5問から3問を選択して解答 |
| 第3時限 15:00~16:30 | 小論文:出題テーマから一つを選択して解答 |
| 科目 | 機械工学基礎 機構学・機械要素設計、機械力学、制御工学、工業材料、材料力学、流体・熱工学、工作設計管理関連課題 機械設計に関わる管理・情報等に対する知識 機械設計基礎課題 機械設計の基本となる計算課題を含む知識 環境経営関連課題 機械設計の管理者として必要な環境・安全に対する知識 実技課題 (問題選択方式) 設計実務に関わる計算を主体とした問題が複数出題され、その中から指定された問題数を選択して解答 小論文 出題テーマから1つ選択し、1300~1600字程度の論文を作成 |
|---|
<受験料>
33,000(税込み)
<合格率>
年度によって異なりますが、3割程度です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2024年 | 162人 | 53人 | 32.7% |
| 2023年 | 143人 | 52人 | 36.4% |
| 2022年 | 142人 | 47人 | 33.1% |
| 2021年 | 148人 | 56人 | 37.8% |
| 2020年 | 141人 | 47人 | 33.3% |
詳しくは日本機械設計工業会のHPを確認してください。
勉強時間
1級は約200時間勉強しました。2級の時は400時間かかった為、半分の時間で合格できたことになります。時間が限られるなかでの挑戦でしたので、空き時間に可能な限り勉強しました。
仕事は相変わらず9時-21時の毎日でしたので、平日は合計1時間勉強できれば御の字。休日は少なくとも3時間、可能な日は5時間以上していました。総勉強時間が自分的に少なかったので、試験1週間前は追い込みの為毎日定時で上がらせてもらいました。。。業務も繫忙中で申し訳なかったですが、こちらもいろいろ犠牲にしていましたのでやむなしです。
勉強方法
過去問15年分を3周解きました。4年分自費で購入しており、残りは会社にあったものを借りました。1級は過去問の類題が頻出されているため、特に参考書は使いませんでした。ポイントとしては、覚えづらい問題は解説の解き方を繰り返し書いて覚えました。「書く」ことの意味については様々な意見がありますが、私は書くことで記憶が定着し易く感じました。そして小学生の頃に九九を何度も唱えて覚えたように、過去問の解法パターンを覚えました。暗記頼りですね。理論の理解はとても追いつきませんでした。
過去問の入手方法
日本機械設計工業会のHPから入手する
HPより最新の過去問題と一部解答を閲覧することができます。不足する分は電子書籍か紙の過去問集を購入しましょう。
過去問集(紙書籍)を購入する
過去問題が解答付きで販売されています。ネットで購入可能です。
2級までで購入していたものがあれば、ようやく出番ですね。
科目ごとのポイントとおすすめ参考書
設計管理
1-1は穴埋め形式ですね。
設計管理に関しては社内の1級取得者より「ものづくり白書の概要だけは読んでおいた方がいい」と聞いたので、さらっと読みました。小論文の対策としても有効ですので、目を通しておくことをおすすめします。
1-2では、だいたい聞いたこともない横文字についての私見が問われます(例:MaaS,PaaSなど)。横文字の意味がわからなくても、問題文の前後で言っていることの雰囲気から題意を汲み取り、自身の業務環境や経験と絡めて持論を展開しましょう。
機械設計基礎
難易度としては2級の応用総合相当かと思います。実際、応用総合の類題も出題されています。しかし、この機械設計基礎が新規問題で難しい時もあります。そういった時は2限の実技課題が比較的易しくなっていますので、諦めずに食らいつきましょう。完答できていなくても、何かしら考え方があっていれば部分点がもらえるようです。
環境経営関連
2級でも環境安全分野という類似の設問がありましたね。大きく異なるのは記述式の回答になった点です。この科目も環境や社会課題のキーワードに関する知識と併せて「あなたが機械設計技術者としてどう考え、どう対処するか」が問われています。
付け焼き刃の知識を薄く広げるのではなく、自身の業務領域での環境に対する取り組みや、一般市民としての取り組みが書けるとよいかと思います。
実技課題
1級の本丸ですね。おおよそ1,2限で合否が決まる雰囲気があります。小論文は1,2限の出来がボーダー付近の時にプラスになるか否かではないでしょうか。(※あくまで合格時の手応えからの経験則です。)
実技課題は5問中3問の選択です。少しでも解答手順を書けそうな設問に狙いを定めます。
ここで重要なのは、記述式なので部分点を全力で取りに行くことです。全ての問題に目を通してみて、どこかの小問の公式が確実に分かりそうならその設問を選ぶべきです。1問めがわからないからと捨ててしまうのは勿体ないです。私は本番で、加速度と慣性モーメントの問題の解法を書けそうだったのですが、どちらも曖昧でしたので確実に得点できそうなエアシリンダの内径計算を含む大問を選択しました。具体的にR6年の〔4-3〕、〔4-4〕、〔4-5〕を選択しました。〔4-1〕と〔4-3〕で迷って〔4-3〕を選択しました。選択問題もありましたので。
また、解答用紙の計算手順の書き方ですが、私は空欄の一番上に主要公式(最後の答えを導く為の式)を書いて、その横に=最終解答を記載していました。この書き方でも問題なかったようです(結論から述べるスタイル)。その下に順を追って途中式を書いていきました。理由としては公式を忘れる前に書きたかったのと、枠外に書くのは時間ロスになるからです。今思うと、頭から解法が間違っていると×にされるリスクがありましたが、やはり部分的に採点してもらえていることは確実なようです。1限の機械設計基礎も同様です。さらに効果があったかは不明ですが、最終の答えの数値には _,, を書いて強調しました。
小論文
文章を書くのが苦手な人にとっては鬼門かもしれません。私は論文を書いた経験こそ無かったものの、計算に比べて苦手意識は無かったのであまり苦労しませんでした。私は社内の1級取得者(技術士取得者)に添削を依頼していました。他の文章問題と同様、自信の経験や考えとその根拠を記載していきましょう。どうも設問で問われているような設計手法や技術に関する用語は、採点者は当たり前に知っているようなのです。しかし答え方としては「知らない人が読んでも理解できる」ことが重要なようです。自分の世界を展開するあまり、専門的な用語の羅列となって採点者の理解が置いてけぼりになっては高得点を得ることは難しいです。
また、小論文を書くうえで「型(骨子)」を作ることが重要です。私の場合、
・導入(設問で言っていることを肯定、自分の環境での具体例を書く。)
・課題に対する対策①
・課題に対する対策②
・まとめ(対策をなぞって強調、今後の機械設計技術者としての決意表明など。)
上記のような型で、対策①と②は骨子として事前に準備しておいた物を当てはめるのですが、本番では微妙に設問とマッチしなかった為、試験時間中に考えて書きました。内容に正解は無いとのことなので、設問に答えることを意識しましょう。(言いたいことを言うのではなく。)
この本は技術士二次試験の対策も見越して購入しましたが、あまり使用しませんでした。添削でかなり手応えを感じていた為です。小論文に初挑戦で、添削を受けられないという方は読んでみてはいかがでしょうか。添削もSNSで合格者に依頼してみると良いかもしれません。
合格ライン
合格点は公表されていませんが、半分~6割以上の正答が必要になるかと思われます。私は6割程度の手ごたえで、合格することができました。
最後に
難しい試験ですので、合格すると自信が付きます。設計実務者向けの試験ですし、計算力の証明になります。私の場合、転職サイトで大手メーカー複数社からスカウトされるようになりました。よく「意味が無い」と言われますが、そんなことは大抵取っていない人が言っていますので気にしなくて大丈夫です。皆自分のやってきたことを正しいと思いたいなかで、プライドが低く一切そう思わない私ですら「自分なりの目標として精一杯努力する価値のある資格」だと感じています。ぜひ自分を信じて頑張ってくださいね。
機械設計技術者試験を頑張る皆様
— とけい@設計 (@tokei_chu) April 17, 2025
転職で有利になりますよ
私は大した学歴も無く、今大した企業でも無いですが2級を取ったあたりで大手メーカーから開発設計職でスカウトが来るようになりました
例)完成車メーカー3社、メガサプライヤー1社他
計算力の証明になるので学歴コンプは破壊できますよ😁↓
機械設計技術者試験1級に合格しました🎊
— とけい@設計 (@tokei_chu) February 15, 2025
長い道のりだったなぁ🥲
3級で苦戦していた自分がここまで来られるとは思わなかった😓
ようやくスタートラインに立てたでしょうか🤔
今後も試験勉強で得たものを最大限に活かし、極限まで自分の能力を高めていきたいです!
技術士も頑張ります! pic.twitter.com/LlWoIf2B6l